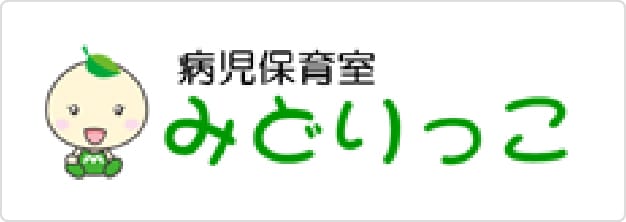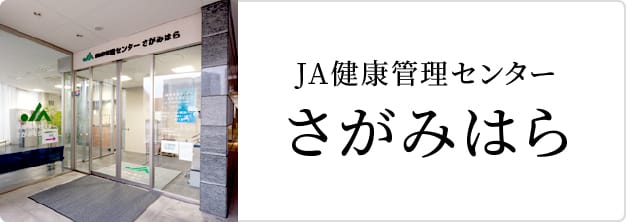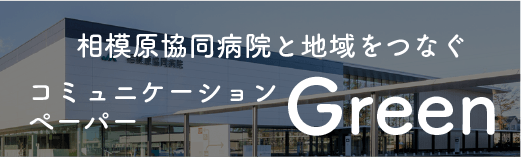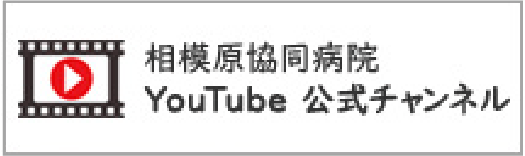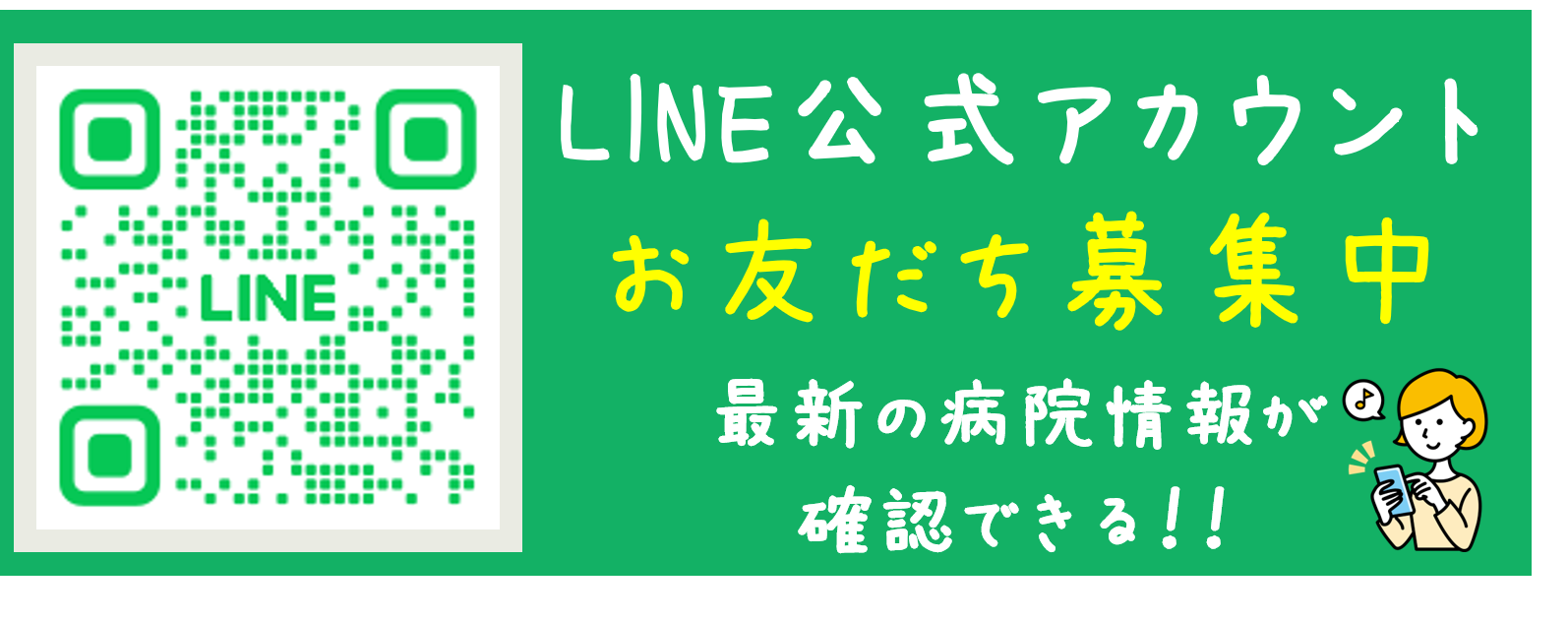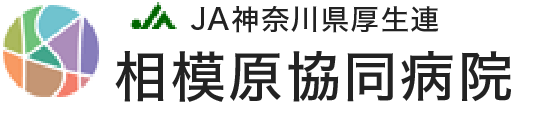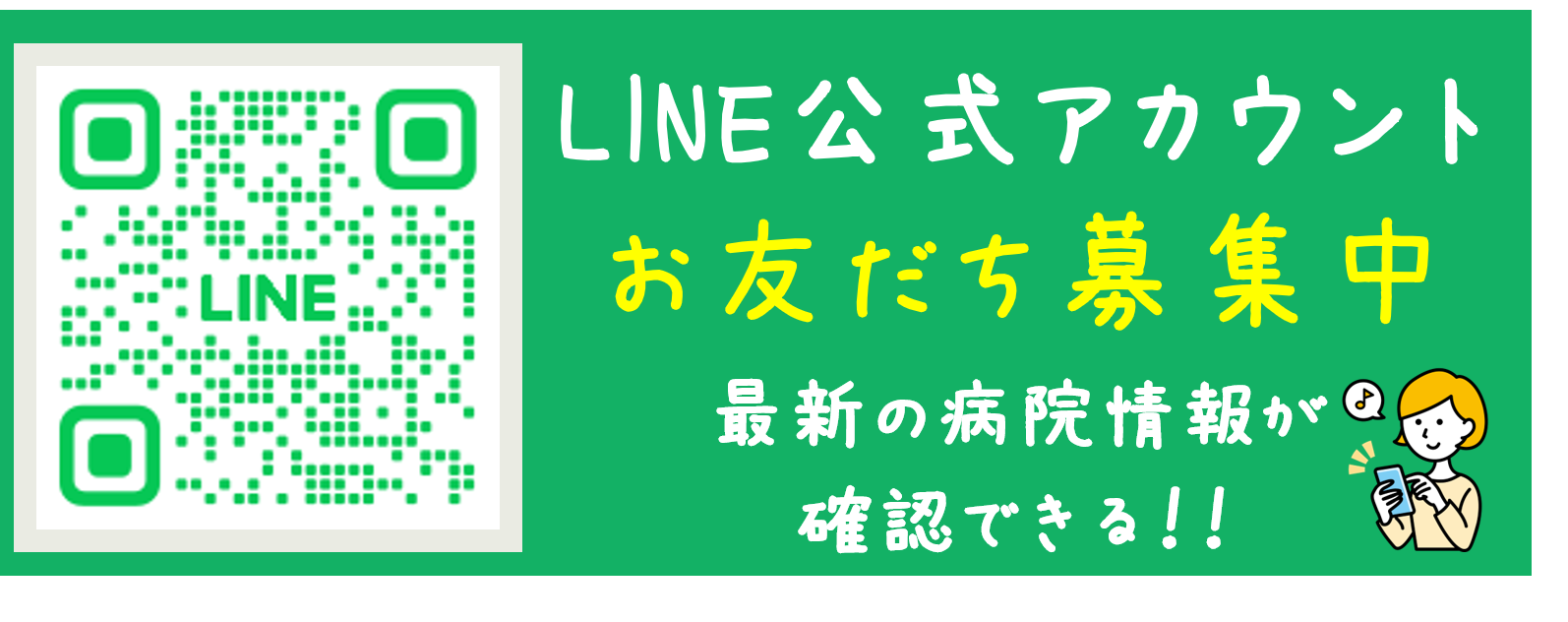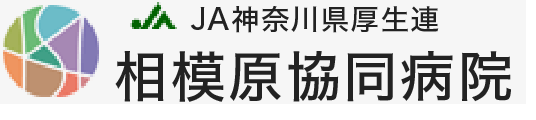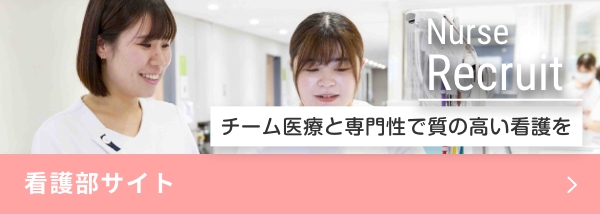部長のつぶやきコラム
- Vol.52【ピアサポート】NEW!
Vol.51【アラジン】
Vol.50【ひとをあやつる】
Vol.49【幸せであること】
Vol.48【コロナにかかりました】
Vol.47【視野が広がり、自分に気づく緩和ケア】 - Vol.46【がんサポさがみ2023のご報告】
- Vol.45【しょっぱいどら焼きの巻】
- Vol.44【自己責任にどう向き合うのかの巻】
- Vol.43【ケアって何?の巻】
- Vol.42【尊厳の巻】
Vol.41【緩和ケアはお節介だの巻 その2】
Vol.40【緩和ケアはお節介だの巻 その1】
Vol.39【緩和×救急の巻】 - Vol.38【病院にくる以前に大事な話の巻】
- Vol.37【青天の霹靂の巻】
- Vol.36【告知と宣告の巻 その2】
- Vol.35【告知と宣告の巻 その1】
- Vol.34【期待外れの巻】
Vol.33【変わらない世の中の巻】 - Vol.32【行きはよいよい帰りはこわいの巻】
Vol.31【やさしさが時にあだになるの巻】
Vol.30【目の前の人を大事にするの巻】
Vol.29【業界用語の壁】
Vol.28【緩和ケア病棟の役割についての巻】 - Vol.27【緩和ケアを受けるには「覚悟」が必要なのか?の巻】
- Vol.26【緩和ケア病棟 お引越しの巻】
- Vol.25【「コロナ禍」と緩和ケア病棟の話】
- Vol.24【団塊の世代と2025年問題の話】
- Vol.23【コミュニケーションの話】
- Vol.22【第50回市民教育公開講座の話】
- Vol.21【「する」と「される」の間の話】
- Vol.20【うまくいかないときの話】
- Vol.19【逆風なのか追い風なのかわからない話】
- Vol.18【自分の存在を肯定できない辛さの話】
- Vol.17【何回も繰り返す話合いのお話】
- Vol.16【専門・認定看護師とチーム医療の話】
- Vol.15【クオリティ・オブ・ライフ(QOL)の話】
- Vol.14【平成最後のチャレンジの話】
- Vol.13【緩和ケア病棟の入院期間についての訂正とその周辺の話】
- Vol.12【後悔のない道を自分で選ぶという話】
- Vol.11【迷惑をかけたくない話】
- Vol.10【心のケアはメニューに載っていない話】
- Vol.9【「私はいつまで入院させてもらえるのですか?」という話】
- Vol.8【緩和ケア病棟はいつ使うところなのか、という話 その2】
- Vol.7【緩和ケア病棟はいつ使うところなのか、という話 その1】
- Vol.6【抗がん剤をやめられない話】
- Vol.5【ボタンのかけ違いの話】
- Vol.4【がまんの話】
- Vol.3【トータルペインの話】
- Vol.2【「診断されたときからの緩和ケア」の話】
- Vol.1【ごあいさつ】
受診について
当院は、地域医療支援病院として、地域の医療機関と日ごろから連携体制を構築しています。診療において紹介患者さんを優先させていただいております。患者さんにおかれましては、この趣旨にご理解いただき、当院を受診される際には、かかりつけ医や他医療機関などからの紹介状をお持ちいただけるようお願い申し上げます。
診療科・部門のご案内
- 臨床研修医募集について(medical_personnel/crr.html)

臨床研修医募集
-

看護師・助産師募集
-

求人情報